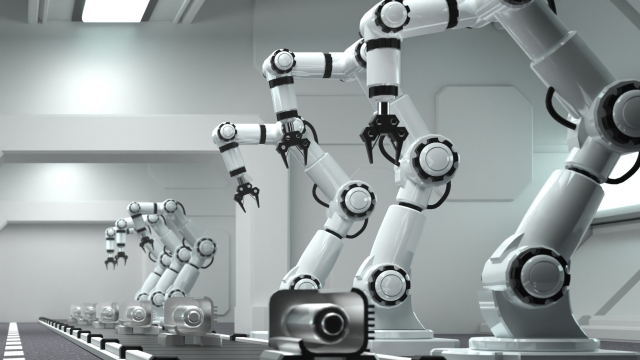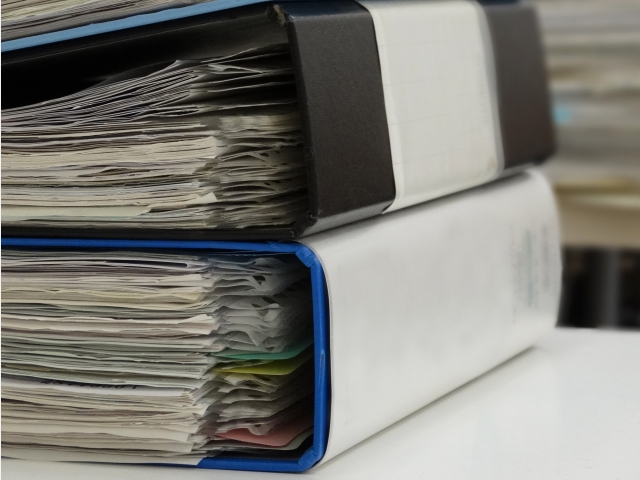人口減少や地域経済の停滞が進む中、日本各地で「行政 × 民間 × 市民」が協働する共創型のまちづくりが広がりを見せています。
その最前線で実践を重ねるのがCOMMON株式会社です。公民連携フォーラムやコモンズコネクト(ネットワーク形成)、公民連携ラボや地域イベント支援などを通じて、地域資源を活かした課題解決型の事業を推進。
単なる都市開発にとどまらず、人と人、組織と地域を結ぶ“関係の再構築”を軸に、持続可能な地域社会の実現を目指しています。

COMMON株式会社の「まちづくり」戦略:公民連携による新しい地域創生
少子高齢化や人口減少、地域経済の停滞など、全国の自治体が抱える課題は年々複雑化しています。
そうした中で注目を集めているのが、「行政 × 民間 × 市民」による共創型のまちづくり。
単なる行政施策や企業CSRではなく、地域の主体者が互いの強みを生かしながら新しい価値を創出する動きです。
この分野で先進的な取り組みを行っているのが、COMMON株式会社です。
公民連携ラボ:多様な主体が出会い、課題を共に考える場
COMMON株式会社が主導する「公民連携ラボ」は、地域課題の発見から解決策の設計までを共創によって進める実践的なプログラムです。
2025年6月に実施されたラボでは、自治体職員、地域企業、NPO、教育機関、住民などが一堂に会し、「行政だけでは解けない課題をどう解決するか」をテーマにディスカッションとワークショップを行いました。
特に印象的なのは、同社が掲げる“つながりから始まる共創”という理念。
会議室で終わらない実践型の学びの場として、行政の枠を越えた自由な発想を促し、地域での実装を目指す取り組みが進んでいます。

公民連携フォーラムin大阪——対話から実装へ、公民が共に地域を動かす
2025年9月に開催された「公民連携フォーラムin大阪」では、行政・企業・団体など約1067名が集まり、“共創による地域課題の解決”をテーマに熱い議論が交わされました。
主催のCOMMON株式会社は、フォーラム全体の企画・運営を担い、登壇者・来場者・後援団体をつなぐ「橋渡し役」として機能しました。
本フォーラムでは、国や自治体の最新動向を共有する基調講演に続き、民間企業による実践事例の紹介や、地域課題をテーマにしたパネルディスカッションを実施。
会場には「公民の垣根を越えた対話」を目的とした自由交流スペースが設けられ、その場から新たな協定・連携が複数生まれるなど、実践につながる成果が数多く生まれました。
COMMON株式会社はこのフォーラムを単なるイベントとしてではなく、“継続的な共創プラットフォームの始まり”と位置づけています。
同社が目指すのは、行政・企業・地域が対話を通じて課題を可視化し、具体的なアクションへと落とし込む「共創の循環モデル」。
その実現のため、今後は関西を皮切りに全国各地での展開が予定されています。
公民連携モデルの構築:資金・人材・ノウハウの“橋渡し役”として
まちづくりを持続的に進めるうえで、最も大きな課題となるのが「資金調達」と「事業推進力」です。
行政予算には限界があり、民間企業の収益モデルだけでは継続性が確保しにくい。
COMMON株式会社は、その中間に立ち、両者の強みを組み合わせる“橋渡し役”として機能しています。
1. 公共事業と民間投資をつなぐ仕組み
同社は、民間企業のマーケティング力や企画力を公共プロジェクトに取り入れる仕組みを設計。
たとえば、地域ブランド創出や空き施設活用のプロジェクトにおいて、スポンサー企業を巻き込みながら「社会的意義」と「経済的持続性」を両立させるモデルを構築しています。
2. 教育・福祉・商業まで広がる連携領域
また、行政・教育・商工・福祉といった分野を横断し、地域全体を一つの「共創圏」として再構築することにも注力。
単発イベントにとどまらず、地域の課題を“ビジネスで解決する”長期的なプロジェクトへと育てる点が特徴です。
地域イベント支援の実践例:寝屋川市「啓明小学校10周年記念」
2025年5月、COMMON株式会社は寝屋川市啓明地域協働協議会からの依頼を受け、啓明小学校の開校10周年記念イベントをプロデュースしました。
この支援は単なるイベント企画ではなく、地域の「つながり」を再構築する試みです。
学校、家庭、地域団体、企業など多様な立場の人々が協働し、企画段階から実施まで一体となって進めました。
COMMON株式会社は、運営ノウハウの共有やボランティアコーディネート、企業協賛の調整など、裏方の支援を担いました。
その結果、イベントは地域全体の絆を深める象徴的な機会となり、住民参加型のプロジェクトが新たに生まれるきっかけにもなっています。
コモンズコネクト—地域と企業をつなぐ“共創人口”の交流拠点
COMMON株式会社が主催の「コモンズコネクト」は毎月大阪、11月より東京も開催されます。
このイベントは、自治体・企業・NPO・教育機関など、分野を越えて地域課題に関わる人々が集う交流の場です。
10月の大阪会場では、泉南市や関西圏の自治体担当者が登壇し、地域の取り組みを紹介。
会場内では民間企業との意見交換が活発に行われ、新たな協働の芽が多数生まれました。
コモンズコネクトの特徴は、“名刺交換で終わらない出会い”をデザインしていることです。
COMMON株式会社は、イベント当日の交流を起点に、後日マッチングや連携協定の支援まで伴走。
単なるネットワーキングではなく、課題解決型のプロジェクトづくりを目的とした継続支援を行っています。
こうした仕組みにより、COMMON株式会社は「関係人口」から一歩進んだ“共創人口”という概念を実践しています。
地域を応援するだけでなく、共に課題を解決し、未来をつくる仲間としての関わりを生み出しているのです。
新しい「まちづくり」の視点:関係人口から共創人口へ

近年、「関係人口」という言葉が注目されています。
地域外の人々が関心を持ち、一定の関わりを持つことを指しますが、COMMON株式会社はさらに一歩進んで“共創人口”という概念を提唱しています。
それは、地域の課題を自分ごととして捉え、共に行動する人たちの総称です。
観光客でもなく、移住者でもなく、「地域の未来を一緒に考える仲間」としての関係を築くことを目指しています。
この発想が、同社のまちづくりをより多様で持続的なものにしています。
今後の展望:全国に広がる「共創のエコシステム」
COMMON株式会社は今後、既存の地域ネットワークをさらに拡大し、「共創のエコシステム」構築を進める方針です。
そのビジョンは、「地域ごとに異なる課題を、共創によって可視化し、解決へ導く社会インフラをつくる」こと。
1. デジタル連携の強化
オンラインプラットフォームを通じ、自治体・企業・住民の間でプロジェクト情報を共有する仕組みを整備。場所にとらわれず、どこからでも地域貢献ができる仕組みを目指します。
2. 若者・企業との協働
若年層の参加を促すため、大学やベンチャー企業との連携も強化。新しい技術や発想を地域課題解決に取り入れることで、未来志向のまちづくりを実現します。
3. 国や地方自治体との政策連携
国の地方創生推進交付金制度や自治体のまちづくり補助金などを活用し、資金調達の仕組みを体系化。
持続可能な事業設計を通じて、全国各地で再現可能な公民連携モデルを確立していく構想です。
共創が導く“人を中心とした地域再生”
COMMON株式会社のまちづくりは、施設やインフラ整備にとどまりません。むしろ、人と人、組織と組織を結びつける“関係の再構築”を中核に据えています。
地域イベントの企画から行政との協働事業、企業連携、教育支援に至るまで、すべての活動に一貫するのは「共創」の姿勢です。
課題を共有し、アイデアを出し合い、実行まで伴走する—その積み重ねが、地域社会の新しいかたちをつくり出しています。
今後もCOMMON株式会社は、地域に眠る資源と人の力をつなぎ、“課題をビジネスで解決する”という理念のもと、全国各地で持続可能なまちづくりを推進していくでしょう。

会社概要
会社名 COMMON株式会社
代表者 増田 勇樹
住所 京都府京都市下京区花屋町通櫛笥西入薬園町170-2
ビジネスeye
代表の増田氏は、長年にわたり自治体との関係構築に力を注いできました。
今年は大阪で、自治体と企業をつなぐ大規模イベントを開催し、約1,000人を集客する成功を収めています。
こうした実績を通じて、地方公共団体や自治体、政治関係者などから厚い信頼を獲得してきました。
単なるイベント開催やスポーツ振興を通じた地域活性化にとどまらず、企業と自治体が連携し、持続可能なビジネス関係を築いている点が特徴です。
今後は、より迅速なビジネスマッチングと自治体との協働体制を強化するため、システム化にも取り組むとのことです。
中央と地方、そして企業を新たな形でつなぐこの取り組みが、日本全体の活力を取り戻す契機となることが期待されます。
当メディアでは、同社の今後の事業展開を引き続き注視し、レポートしていきますのでご期待ください。