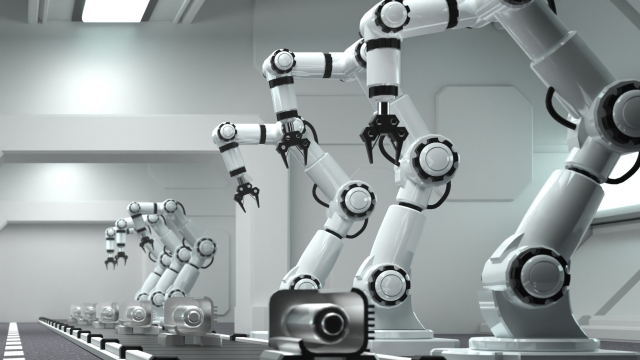人口減少社会の中、豊かで多様性のある社会を築くためには、人口の半分を占める「女性の力」を最大限に引き出すことが不可欠である。
しかし、世界経済フォーラムが発表した各国の男女間格差を数値化した「ジェンダー・ギャップ指数」において、日本は148か国中118位(2025年版)と、世界から大きく後れを取っているのが現状だ。
こうした中で東京都は、東京のみならず日本全体に女性活躍の輪を拡げていくため、これまで推進してきた働く女性の活躍を促進する様々な取組を「女性活躍の輪~Women in Action~」(WA)として位置づけ、積極的に発信している。
誰もが自らの生き方を性別にとらわれず選択できる社会の実現に向け、東京から女性の活躍を後押しするムーブメントの“輪”を拡げているのだ。今回は、日本の現状と課題、そして東京都が展開する具体的な施策について紹介する。
世界から取り残される日本のジェンダー格差
世界経済フォーラムの「ジェンダー・ギャップ指数(2025年版)」で、日本は148か国中118位、G7で最下位という結果であった。
「教育」「健康」のスコアは高いものの、「政治参画」「経済参画」の値が著しく低いことが要因となっている。
国内に目を向けると、1985年に男女雇用機会均等法が成立し、今年で40年を迎えた。
この間、女性の就業率は1984年の48%から2024年には54%へと上昇し、特に第1子出産後に正社員で就業を継続する女性の割合は、1980年代の40%から2010年代には83%へと大幅に増加するなど、確かな成果も見られる。
しかし、課題は山積している。家事・育児に費やす時間は依然として女性に偏り、男女間の賃金格差や管理職に占める女性割合の低さも解消されていない。
幼少期の「男の子だから・女の子だから」といったバイアスに始まり、理系分野に進む女子学生の少なさ、出産・育児期における「マミートラック」と呼ばれるキャリアアップの停滞、親の介護による離職、老後の年金格差など、女性はライフステージごとに様々な課題に直面しているのが現実である。
こうした中、東京都は意思決定の場への女性参画を積極的に進めている。
小池都知事が就任した翌年の2017年(平成29年)に28.5%だった都の審議会等における女性委員の任用率は着実に上昇を続け、2024年(令和6年)には47.2%に達し、ほぼ半数を女性が占めるまでになった。
経済成長の鍵を握る女性活躍
女性活躍の推進は、社会の公平性だけでなく、企業や経済全体の成長にも直結する重要なテーマである。
内閣府の調査によれば、7割近くの機関投資家が、女性活躍に関する情報を「企業の業績に長期的には影響がある情報」と捉え、投資判断の参考にしている。
実際に、女性役員比率が高い企業は、そうでない企業に比べてROE(自己資本利益率)やEBITマージン(支払金利前税引前利益と売上の比率)といった業績指標が高い傾向にあるというデータもある。
マクロ経済の視点では、女性の活躍がもたらすインパクトはさらに大きい。
男女間の賃金格差や労働参加率の差などが完全に解消された場合、女性の給与総額は約81兆円増加し、それに伴う消費も約44.5兆円増加する可能性があると試算されている。
また、2040年にかけて女性の労働力人口比率が男性並みに上昇すると仮定した場合、実質GDP(国内総生産)は約40兆円押し上げられると見込まれており、女性活躍が日本経済の持続的な成長に不可欠であることがわかる。
多角的なアプローチで女性を支える東京都の施策
東京都は「女性活躍の輪~Women in Action~」のスローガンの下、会議・カンファレンス、企業・スタートアップ支援、キャリア支援・相談、若者支援、表彰制度、健康・ヘルスケア、都庁職員向け施策といった幅広い分野で具体的な取組を展開している。
例えば、経営者の意識改革を促す「東京女性未来フォーラム」では、2025年には130社を超える企業が賛同し、共同宣言を行うなど、企業の垣根を越えた輪が拡がっている。
また、女性起業家の成長を支援するプログラム「APT Women」では、2017年の開始からこれまでに計280名を支援し、資金調達額は合計240億円以上にのぼる。
若者支援も手厚い。STEM(科学・技術・工学・数学)分野での女性活躍を推進するため、女子中高生向けのオフィスツアー「Girls Meet STEM in TOKYO」を実施。
2025年度には実施企業を50社以上に拡大し、将来の進路選択を後押しする。
これらの施策は、女性が直面する様々な課題に対し、ライフステージのあらゆる段階で切れ目なくサポートを提供することを目指している。

東京都 産業労働局 働く女性応援担当部長の吉浦宏美氏は、都の取り組みについて次のように語る。
「東京都では『女性活躍の輪』というシンボルマークを掲げ、女性をバックアップする施策を幅広くPRし、推進しています。
今回の講演会もその一環です。本日いただいたような言葉を皆さまと共有しながら、女性が活躍できない障害があれば、様々な角度からバックアップする施策を展開していきたいと考えています。
例えば、理系やIT職を目指す女性が少ないという課題に対し、都で講座を用意し、就職まで橋渡しをする事業を展開しています。
また、もっと若い世代、特に中高生の皆さんに、理系分野での将来の姿を見てもらい、関心を持ってもらえるような機会も幅広く提供しています。
小池都知事が就任されてから、これらの動きは非常に活発になりました。私たち職員も、リーダーである知事が道を切り拓いてくださることで、自信を持って仕事に取り組むことができています」
8月25日には小池都知事を迎えたイベントも開催
2025年8月25日、有楽町のTokyo Innovation Baseでイベント「Women in Action: Choosing Your Career」が開催された。
当日は、コロンビア大学ビジネススクール教授のシーナ・アイエンガー氏による基調講演や、アサヒグループホールディングス株式会社の小路明善会長、小池百合子都知事、そしてモデレーターの株式会社タレイリスト代表取締役兼CEOの塚原月子氏を交えたパネルディスカッション、さらには都内の高校生との意見交換会が行われた。

シーナ・アイエンガー氏
「私たちは、自分の人生の物語を運命や偶然ではなく、『選択』というレンズを通して見ることを学ぶべきです。
選択とは、単なる自己表現ではなく、創造の行為。現代のヒーローは『選ばれし者』ではなく、自らの選択を通して自分自身を作り上げた『選ぶ者』なのです」

小路明善氏
「ジェンダーギャップをゼロにするには、環境、制度、意識の3つの改革が必要です。
特に制度面では、単なる機会の平等だけでなく、男女間の体力差なども考慮した『結果の平等』をどう盛り込んでいくかを考えていかなければなりません」

小池百合子都知事
「女性が持つ力を社会で生かすことが、東京を元気にし、世界一の都市にすることにつながります。
自分に制約を設けず、まずチャレンジすることが大切。ダメな理由を考える前に、できることを進めていってほしいと願っています」

意見交換会では、都内の高校生から登壇者へ活発な質問が寄せられた。
「男女の賃金格差に対し、私たちに何ができるか」
これに対し小池都知事は、「問題意識を持ち、アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)を打ち破るべく、積極的に挑戦してほしい」とエールを送った。
「未来を考えると自分の限界を決めてしまう。女子高生へのアドバイスは」
アイエンガー氏は「夢は無限に湧き出てくるもの。粘り強く、あなたを信じてくれる人を見つけ、決して諦めないで」と力強く語った。
「女性が少ない職場で孤立した時の心の持ちよう」
アイエンガー氏は「大きな目標を見失わず、時には裏口から入るようなアプローチも必要」とアドバイスした。
「政治の場でリーダーシップを発揮する中での困難は」
この質問に小池都知事は、「私自身は男女を意識することなくやってきた。困難なこともチャレンジであり、やりがいがあると言い聞かせている」と自身の経験を語った。
社会の構造的な課題から個人のキャリアの悩みまで、東京都の取り組みは多岐にわたる。
これらの施策が着実に実を結び、一人ひとりが性別に関わらず、自らの可能性を最大限に発揮できる社会が実現されることは、東京だけでなく、日本全体の未来を明るく照らすだろう。
その“輪”が全国へと拡がっていくことに、大きな期待が寄せられる。