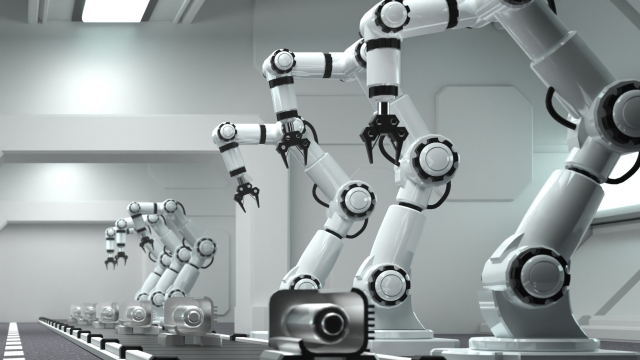生成AIやAIエージェントの利用が広がっていますが、同時にセキュリティの問題や著作権侵害のリスクなどが言われています。
トラブルを起こさないためには、AI導入時からどういう利用の仕方をして、どの部署がどのように利用するのか明確に定義しておき、やってはいけないことを決めておくことが重要です。
企業が生成AIやAIエージェントを利用する時にAI利用規程などのルールが必要な理由とは?

企業が安心してAIを活用するための第一歩がセキュリティ対策や情報漏洩対策、著作権侵害対策です。
AI(人工知能)の活用が急速に広がる中、企業や自治体がAIを導入する際に「AI導入規程」を策定する動きが加速しています。単なるAIの導入ではなく、組織全体で安全かつ効果的にAIを活用するためには、明確なルールと指針が不可欠となってきています。
なぜAI導入規程や利用ガイドラインが必要なのか?
1. 情報漏洩や法令違反のリスク回避
AIは大量のデータを扱うため、個人情報や機密情報が誤って外部に漏れるリスクがあります。また、生成AIでは著作権侵害や虚偽情報の生成(ハルシネーション)も懸念されます。規程やルールを設けることで、こうしたリスクを未然に防ぐことができます。
2. 業務の混乱を防ぐための明確な運用ルール
誰が、どの業務で、どのようにAIを使うのかが曖昧なままでは、現場での混乱や誤用が発生します。AI導入規程やガイドラインは、業務範囲や責任の所在を明確にし、従業員が安心してAIを活用できる環境を整えます。
3. 従業員のリテラシー向上と活用促進
AI利用規程や利用ガイドラインを通じてAIの正しい使い方を教育することで、従業員のITリテラシーが向上し、AI活用が組織全体に広がります。結果として、生産性向上や業務効率化にもつながります。
4. 導入効果の最大化とROIの明確化
AI導入にはコストが伴います。規程により目的やKPIを明確に設定することで、導入効果を定量的に測定し、費用対効果(ROI)を可視化できます。
AI導入規程に盛り込むべき主な項目
- AI活用の目的と対象業務
- 利用可能な業務範囲の定義
- 機密情報・個人情報等の取り扱いルール
- 著作権・倫理的配慮に関する指針
- トラブル発生時の対応フロー
- 従業員向けの教育・リスキリング方針
- AI利用規程や利用ガイドラインの定期的な見直し
まとめ
AI導入は単なる技術革新ではなく、組織文化や業務プロセスの変革を伴う取り組みです。
だからこそ、導入前に「AI導入規程」「AI利用規程」「AI利用ガイドライン」を整備することが、成功への第一歩となります。
ルールがあることで、AIの可能性を最大限に引き出し、安心・安全な活用が実現できるのです。
AI導入について詳しく聞きたい場合は、下記にお問合せください。
AI導入・利用に関する問合せ先の会社概要
会社名:合同会社デジタリアン
住所 :東京都新宿区西新宿
代表 :代表社員 山下 泰弘

ビジネスeye
AIを利用する社内ルールがないと、情報漏洩や著作権侵害などのリスクが増加することになります。
社内ルールは、規程やガイドラインとして制定するものですが、規程やガイドラインがないことで発生した重大なトラブル事例には、情報漏洩や誤情報の拡散、著作権侵害などが数多く報告されています。
ルール無きAIの利用で発生したトラブルの代表的な具体例
社内機密情報の流出
- 韓国サムスン電子では、生成AI(ChatGPT等)活用時の指針が曖昧だったため、従業員が社内ソースコードや議事録など機密情報をAIに入力し、それらが外部へ漏洩しました。
- ポリシー策定後、社内機器でのAI利用禁止や、個人端末でも機密情報入力禁止など厳しいルール整備に至りました。
AIが生成した誤情報の拡散
- 福岡県の自治体後援キャンペーンサイトで、AIが書いた記事に実際には存在しない観光名所が掲載され、多数の指摘を受けてサイト閉鎖に至りました。
- これは利用規程もチェック体制もないままAIを使い、誤情報の発信リスクが現実化したケースです。
著作権侵害の問題
- 画像生成AIで作成したイラストが有名キャラクターに酷似していたことで、投稿削除などの措置が取られる事例が多発しています。
- 商用利用などでAIが出力したコンテンツが他人の権利を侵害したにも関わらず、明確な利用規程や審査体制が未整備でトラブルが広がっています。
ポリシー不足による一般的リスク
- 調査によれば、職場の6割以上がAIを利用しているにもかかわらず、2割未満しか明確な利用規程やポリシーを認知していないという深刻なギャップが報告されています。
- 規程不在のままAI利用が広がると、情報漏洩・コンプライアンス違反・不適切アウトプット・内部統制の欠落など多面的なリスクが顕在化するとの指摘があります。
他業種での実例
- 製造業ではAI運用指針未整備のために導入効果が出ず、小売業ではデータ活用設計ミスによるトラブルが起きています。
教訓と対策
- 適切なAI利用規程がないことが重大トラブルのきっかけになりうるため、具体的なガイドライン策定と従業員教育、技術的対策(情報漏洩防止機能など)の導入が必須とされています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
執筆・編集者
ビジネスeye編集部
山下泰弘
【執筆者略歴】
通信販売業の企業で経理として上場準備業務等に従事し、IPO達成。その後、IPO準備のITモバイルベンチャーにてIPO準備、資本政策等に従事。転職後、エンターテインメント業の上場企業にて経営企画部長、管理本部長として管理部門を統括、海外企業の買収、資本政策立案から実行まで担当。管理・経営企画の現場実務の経験多数。その後、ITサービス業のマザーズ上場企業を経て、不動産系企業にてCFO、ITマーケティング企業でCFOとして上場準備業務に従事。
現在は、合同会社デジタリアン代表として、IPO支援とAI導入支援を通じてベンチャー企業育成に力を入れている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー