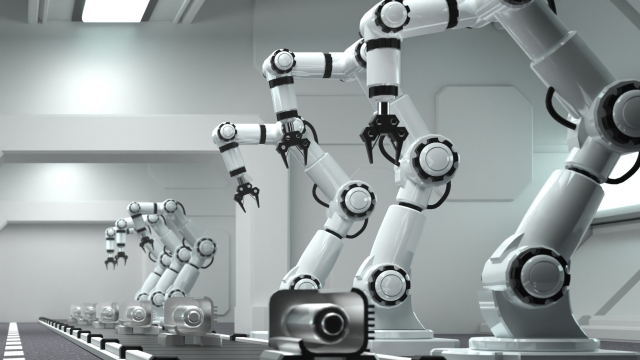小売業でAIを活用する方法は在庫管理と発注のリードタイムの最適化だと言われています。
他の活用方法としては、マーケティングの最適化でしょう。
広告のキャッチフレーズやペルソナの最適化がすでに実現されていると言われています。
小売業界は労働力不足や市場の縮小等、日本経済全体が抱える問題とは無縁ではありません。
これらの状況のもと、AIの活用で活路を見出そうとしている企業があります。いち早いAI導入が業績の差に直結しているようです。

2025年小売業界が抱える主な業務上の課題
労働力不足と生産性低下
- 少子高齢化による生産年齢人口の減少で、現場作業者の確保が困難に。
- 人件費の上昇が企業コストを圧迫し、利益率悪化の要因に。
市場縮小と消費行動の変化
- 総世帯数の減少にともない小売市場全体が縮小傾向。
- 高齢化による消費ニーズの質的変化や、都市部と地方での商圏の変化に対応が必要。
デジタル化・DX推進の遅れ
- 既存レガシーシステムの刷新遅延(「2025年の崖」問題)による業務効率化の阻害。
- ネットショッピングなど消費者のデジタル対応進展に追随したビジネスモデル転換が急務。
業務の属人化・効率化課題
- 現場業務の属人化により標準化や効率化が進まない。
- 発注・在庫管理・販売促進などでAI導入や業務自動化が必要とされている。
地域課題対応の必要性
- 高齢者が移動に困難を抱える地域での生活圏内ショッピングや宅配など新たな購買支援態勢の構築。
- 移動手段提供や高齢者見守りサービスなど、小売を超えた地域課題への対応も求められている。
これらの課題を背景に、小売企業は生産性向上、デジタル技術の積極活用、地域密着型サービスの強化に取り組む必要があります。
2025年の小売業が抱える課題に対して、AIでできる主な解決策
労働力不足・人件費増加への対応
- 接客チャットボットや音声AIアシスタントで問い合わせ・商品案内対応を自動化し、スタッフの負担軽減。
- AI搭載セルフレジや無人店舗技術でレジ業務の効率化。
- AIによる人員配置最適化で少人数運営の実現。
在庫管理・廃棄ロス削減
- 需要予測AIによる仕入れ・発注の自動最適化で欠品・過剰在庫を抑制。
- リアルタイム在庫管理AIで品切れや陳列ミスを即時検知し迅速な補充を促進。
- 発注業務の自動化で発注ミスや属人化を防止。
業務標準化と作業効率向上
- RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入し勤怠管理、棚卸し、レジ精算など定型業務を自動化。
- AI搭載ツールで業務の属人化を解消し、業務のバラつき・ムダ軽減。
マーケティング・顧客体験の向上
- AIによる顧客データ分析でパーソナライズされた販促やキャンペーンを自動配信。
- 店舗のAIカメラで顧客行動解析し、店舗レイアウトや人員配置に活用。
物流・配達の効率化
- AI活用による配送ルートの最適化、人手不足を補う無人配送や倉庫作業の自動化。
- サプライチェーン全体の需要予測連携で欠品防止とコスト抑制。
これらAIの活用により、小売業は人手不足や業務効率化、マーケティングの高度化といった複合的な課題を解決し、持続可能な成長を目指しています。
在庫過多と欠品をAIで同時に減らす実装手順
AIによる在庫最適化の実装手順
- データ収集と統合
- 過去の販売実績データ、商品の入出庫履歴、季節や天候、販促イベント、外部経済指標などを体系的に収集。
- 店舗別・商品別など詳細なデータ構造に統合し、リアルタイムでも更新可能な基盤を作る。
- 需要予測モデルの構築
- 時系列解析や機械学習、深層学習(例:LSTM、ARIMA、XGBoostなど)を用いて、商品・店舗ごとの需要予測モデルを作成。
- 過去データに基づいて販売量の季節性やトレンド、外部変数の影響を学習し、未来の売上・需要を高精度に予測。
- 適正在庫量の算出
- 需要予測結果とリードタイム、発注・補充のコストバランスを踏まえ、各商品の最適な在庫水準を算出。
- 欠品リスクと過剰在庫リスクを定量化し、それぞれを最小化するための在庫戦略を設定。
- リアルタイム在庫モニタリング
- AIカメラやIoTセンサーを用い、倉庫や店舗の在庫をリアルタイムで監視。
- 在庫数の変動に応じて不足を自動検知し、早期発注や補充シグナルをシステム発信。
- 自動発注システムの実装
- 予測と在庫状況をもとに、一定の閾値を下回った際に自動的に発注が行われる仕組みを導入。
- 人為的な発注ミスや遅延を排除し、欠品を未然に防止。
- 継続的なモデルの検証・改善
- 実績データと予測結果を比較し精度評価を実施。
- モデルの再学習やパラメータ調整を定期的に行い、変動する市場環境に対応できる体制を維持。
このプロセスにより、AIは過剰在庫と欠品の双方をバランスよく抑え、在庫コスト削減と顧客満足度向上を実現します。

ビジネスeye
実際のAI導入企業の具体例について見ていきましょう。
大丸松坂屋百貨店・東京店ベーカリー部門では、2023年2月にAI需要予測システムを導入し、実証期間の3か月で売上が前年同期比約67%増加するという成果を挙げました。
事例の背景と課題
- 導入前は人気商品の欠品が頻発し、正確な発注が難しい状況でした。
- 廃棄ロスも大きな負担となっていました(約40万円分)。
AI導入の内容
- AIが日々の販売データを解析し、天候や曜日などの外部要因も活用して最適な発注量を自動予測。
- 現場のIT未経験スタッフでも利用できるように設計され、推進チームは着実な現場訪問・検証を繰り返し、運用が定着しました。
導入後の成果
- 売上高が3か月で前年同期比約67%アップ。
- 約40万円分の食品廃棄ロス削減も実現。
- 発注業務が自動化され、スタッフの業務負担も減少。
この事例は、現場に専門知識がなくても、AI導入と継続的な運用改善により大きな売上増を達成できる好例となっています。
導入したAIはどの需要予測手法を使っていたか
小売業で売上を67%改善した事例で導入されたAI需要予測は、販売実績・天候・曜日やイベントといった多様なデータから機械学習手法(主に回帰分析や時系列解析、深層学習アルゴリズム)を使用して予測モデルを構築しています。
需要予測AIの手法構成
- 回帰分析:複数の要因(販売履歴、天候等)による売上の変動を分析し、今後の売上を数値として予測します。
- 時系列解析モデル:過去の販売データや季節性・周期性を分析することで、日々や週ごとの需要変動を精度高く予測します。
- 機械学習・深層学習:膨大なデータからパターンを自動抽出し、未知・複雑な相関関係(天候と需要、SNSトレンド等)も予測に反映させます。近年はニューラルネットワークも活用されています。
手法の特徴
- 従来の「移動平均法」「単純な統計分析」を超え、多変量を学習して精度を向上。
- 現場のIT未経験者でも使いやすいよう自動化・簡単入力化されているため、発注/在庫管理の大幅効率化・ロス減に貢献しています。
このような高度な機械学習や時系列解析アルゴリズムが、売上増加の直接要因となりました。
この小売業AI需要予測で使われていた主要な予測アルゴリズムは、深層学習(ディープラーニング)に基づく多層ニューラルネットワーク、および時系列解析(ARIMAや指数平滑法)です。
主要アルゴリズムの内容
- ニューラルネットワーク(深層学習):過去の売上、天候、イベント、トレンド情報など多変量データを統合し、複雑な需要パターンを自動学習して予測精度を高めます。非線形かつ複雑な関係性も捉えることができ、予測の幅広さ・柔軟性に優れています。
- 時系列解析(ARIMA/指数平滑法):日々・週間・季節単位の売上変動やサイクルを解析し、周期性・トレンドも加味して未来の需要を算出する役割を担います。業界標準として多くの小売企業が導入しています。
実運用上の特徴
- 複数のアルゴリズムを組み合わせ、店舗ごと・商品ごとに最適な予測モデルを自動選定。
- 予測根拠や変数の重みを説明可能な設計(現場と経営双方で納得しやすい運用)。
- IT審査要件なしで容易に使えるノーコード型AIも多く活用されています。
このようなディープラーニング+時系列解析モデルの併用が、売上改善に大きく貢献しました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
執筆・編集者
ビジネスeye編集部
山下泰弘
【執筆者略歴】
通信販売業の企業で経理として上場準備業務等に従事し、IPO達成。その後、IPO準備のITモバイルベンチャーにてIPO準備、資本政策等に従事。転職後、エンターテインメント業の上場企業にて経営企画部長、管理本部長として管理部門を統括、海外企業の買収、資本政策立案から実行まで担当。管理・経営企画の現場実務の経験多数。その後、ITサービス業のマザーズ上場企業を経て、不動産系企業にてCFO、ITマーケティング企業でCFOとして上場準備業務に従事。
現在は、合同会社デジタリアン代表として、IPO支援とAI導入支援を通じてベンチャー企業育成に力を入れている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー