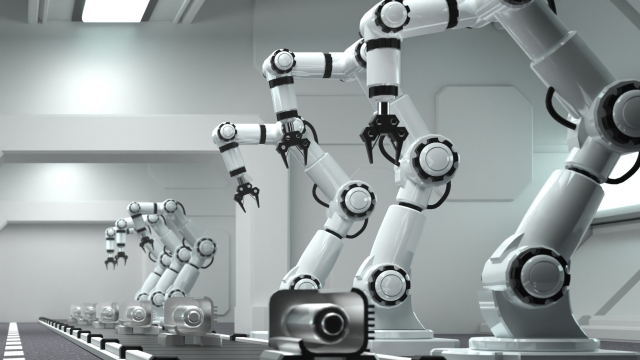東京都は、都民や大学研究者から事業提案を募集し、都民の投票によって選ばれた事業を翌年度の予算案に反映する「都民・大学研究者による事業提案制度」を実施している。
今年度は都民から1,094件、大学研究者から35件の事業提案が寄せられ、審査の結果、都民提案12件、大学提案8件が投票対象として選定された。これらの事業案について、都民によるインターネット等での投票がすでに開始されている。
投票結果を踏まえ、選ばれた事業案は令和8年度の予算案に反映される予定だ。
この制度はどのような経緯で始まり、どのような仕組みで運営されているのか。制度を担当する東京都財務局の担当者にお話を伺った。
担当者インタビュー

お話を伺った東京都 財務局 主計部 政策評価担当課長 田中健太郎さん
Q. 都民・大学研究者による事業提案制度は、どういった経緯で、またどういった目的で開始されたのでしょうか。
目的は二つあります。
一つは、都政が抱える課題解決に向け、従来の発想にとらわれない新たな視点から都民一人ひとりの声を直接反映させることです。
もう一つは、都内に数多くある大学の研究者が持つ知見を都政に活かし、東京の課題解決につなげることです。
大学と研究者、そして東京都が連携協働して事業を作り、より良い都政を実現するためにこの制度が始まりました。
経緯としては、小池都知事の就任後に行われた都政改革の一環として、予算編成のプロセスを見直す中で、都民の皆様の声を直接都政に反映する仕組みとして、都民が提案し、都民が選ぶという制度が構築されました。
Q. 今回で何回目になりますか?
都民提案は平成29年度から始まり、今回で8回目です。大学研究者からの提案は平成30年度からで、今回が7回目となります。
コロナ禍で若干の中断はありましたが、基本的には毎年継続して実施しています。
Q. これまでの投票結果から実現した事業には、どのようなものがあり、どういう成果を上げましたか?
都民提案の代表例としては、防災対策の一環で「東京備蓄ナビ」というウェブサイトを制作しました。これは、サイト上で家族構成などを入力すると、その家庭で最低限備蓄しておくべき水や食料の量が自動で計算され、さらに購入先のリンクも表示されるというものです。
「いざという時に必要な備蓄量がすぐわかるサイトが欲しい」という都民の方の提案から実現しました。
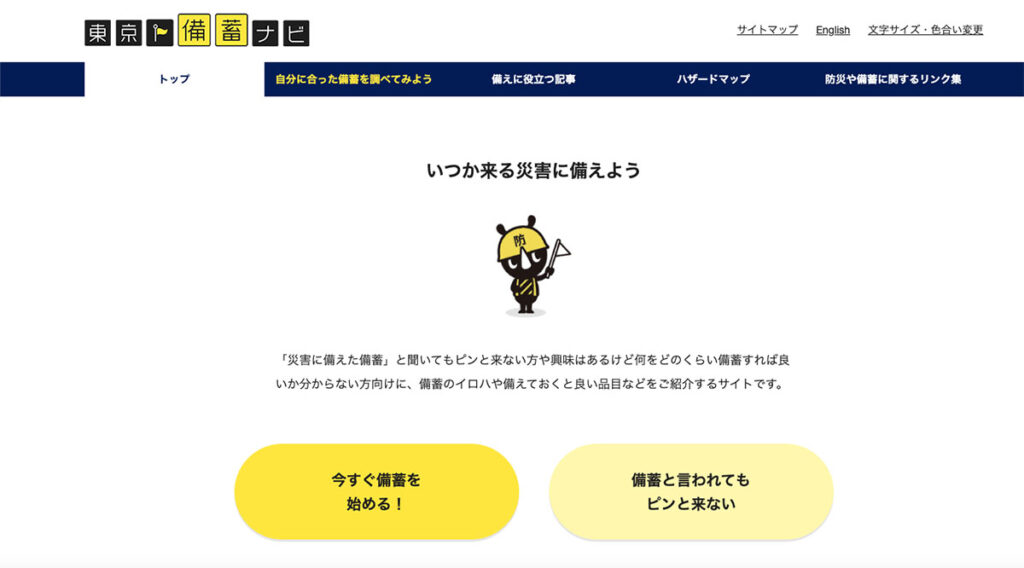
大学提案では、東京大学から提案いただいた『My City Report』というアプリがあります。
これは、例えば歩道のひび割れなどを発見した際に、アプリで写真を撮って投稿すると、その情報が都の道路担当部署に直接届き、迅速な補修につながる仕組みです。
補修の進捗状況もアプリで確認でき、都民と都庁の双方向のコミュニケーションによって、効率的な道路メンテナンスが実現しました。
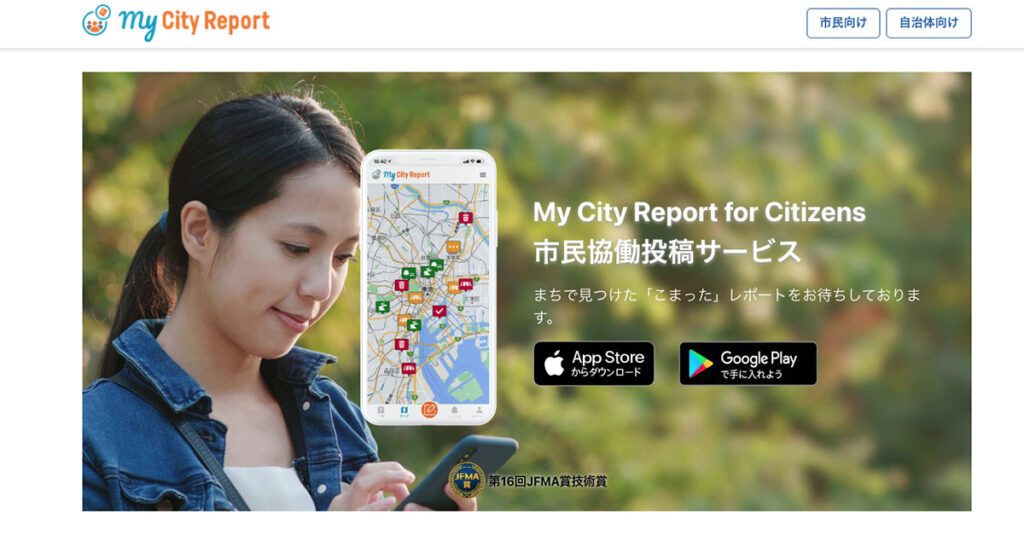
Q. 提案した方が事業を直接作るのでしょうか?
いいえ、都民の方にはあくまでアイデアを提供していただきます。
いただいたアイデアをまず都庁内で審査し、事業化できそうなものを投票対象として選定します。
そして都民の皆様の投票で選ばれた事業を、東京都の担当部署が予算化し、事業として構築していく流れになります。
Q. アイデアが採用された提案者への報酬はあるのでしょうか?
直接的な賞金のようなものはありませんが、投票でアイデアが選ばれた方には、年明けに知事から直接感謝状をお渡しするイベントを設けています。
Q. 都民提案1,094件から12件、大学提案35件から8件が選ばれていますが、選定の基準やプロセスに違いはありますか?
はい、異なります。都民提案は、まず「単年度で完了する事業」「予算上限2億円」といった形式的な要件で審査します。
次に、福祉や防災など、それぞれのテーマを所管する部署が、都の施策の方向性と合致しているか、既存の事業と重複していないかなどをチェックし、絞り込んでいきます。
一方、大学提案も同様に都庁内で審査しますが、それに加えて外部の有識者による専門的な審査も行います。
提案した大学名などは伏せた上で、公平性を保ちながら審査を進めています。
Q. 投票の仕組みについてお伺いします。投票できるのは満15歳以上ですが、理由はありますか?
当初は満18歳以上でしたが、より若い世代の意見を反映させるため、令和3年度から満15歳以上に引き下げました。
中学校3年生で地方自治の仕組みなどを一通り学習し終えることから、義務教育を終えた満15歳以上とすることが妥当だと判断しました。
Q. 都民提案と大学提案、それぞれ3票まで投票できるのはなぜですか?
投票で選ばれる事業は一つではないため、都民の皆様が良いと感じたものに幅広く投票していただきたいという思いから、それぞれ最大3票まで投票できるようにしています。
なお、システム上、都民提案と大学提案から最低1票ずつは投票していただく形になっています。
Q. 投票時に事業案への改善意見を書き込めるようですが、その意見はどのように反映されるのですか?
投票期間中にいただいたご意見は、投票で選ばれた事業を担当する部署にまとめてお渡しします。
担当部署は、その意見を参考にしながら事業を具体的に構築し、予算要求を行いますので、事業化のプロセスの中で改善提案を反映させることが可能になっています。
Q. 1位で選ばれた事業は必ず実施されるのでしょうか?
はい、投票で選ばれた事業は、予算化に向けて進めていきます。
そもそも投票にかけている事業案は、事前に庁内で審査し、実現可能性があると判断されたものになりますので、都民の皆様の投票で選ばれた事業については全て実施する形になります。
Q. 最後に、今回の都民投票について、都民の皆様へメッセージをお願いします。
この制度は、ご自身の提案や投票という行動を通じて、都政に直接参加できる非常に良い機会です。
投票で選ばれたものが、来年度の東京都の事業として実施されます。8月31日まで投票を受け付けていますので、ぜひ多くの方にご参加いただきたいです。
また、これをきっかけに制度を知った方には、来年の春に募集が始まる次の提案にも挑戦していただけると嬉しく思います。
東京の未来を、あなたの一票で
インタビューで語られたように、この制度は都民が「選挙」以外で都政に直接関わることのできる貴重な機会である。
普段感じている課題や「もっとこうなれば良いのに」という思いを、具体的な事業として形にできる可能性を秘めている。
今回投票対象となっているのは、「子供食堂普及啓発事業」や「認知症のある高齢者の行方不明対策」といった都民提案、「首都直下地震対応へ、『揺れ』を感じて・測って・備える、都市と都民の強靭化事業」や「“東京の猛暑・熱中症から都民を守る”最新熱中症予防研究の社会還元事業」といった大学提案など、防災、医療、環境、共生社会の実現など、多岐にわたる分野の事業案だ。
自分たちの暮らしをより良くするため、そして東京の未来を創るために、まずはどのような提案があるのかを知り、あなたの一票を投じてみてはいかがだろうか。
<投票の概要>
投票期間/令和7年7月31日(木) 14時から同年8月31日(日) 23時59分まで(郵送は必着)
投票対象者/令和7年4月1日時点で満15歳以上であり、投票を行う時点で都内にお住まいの方
投票方法/インターネットまたは郵送
投票ページ/https://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/zaisei/zaisei/teian/tomin_touhyou_2025