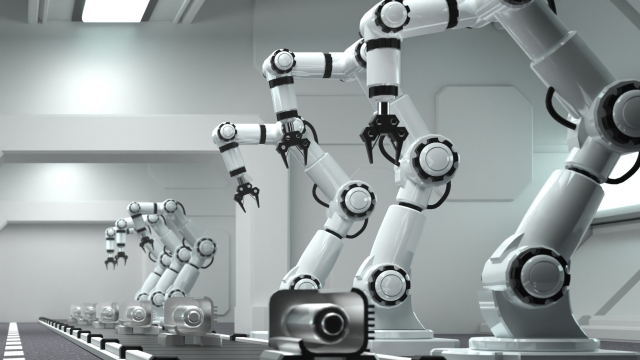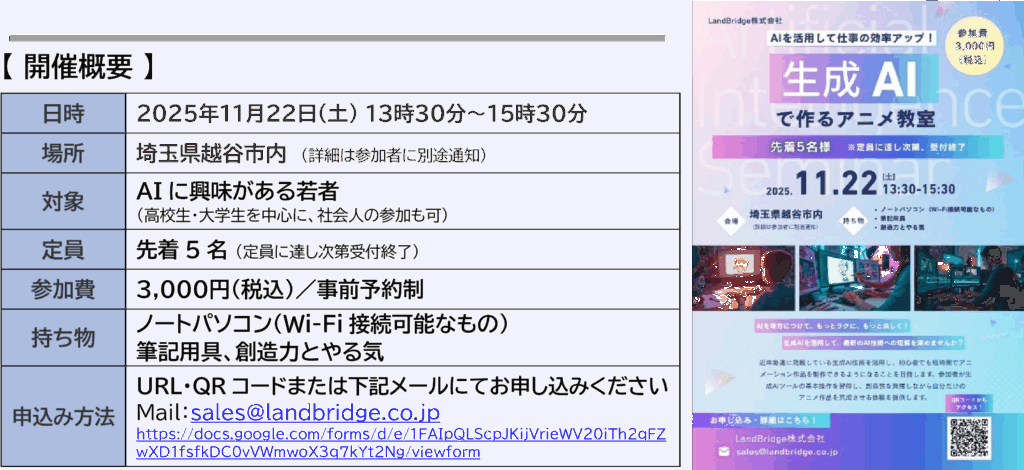警察官から転身してIT企業の経営者になり、年商も億を超えるほどの成長を実現している注目の経営者が三森一輝氏です。
2022年創業のLandBridge株式会社(本社:埼玉県越谷市、代表取締役:三森一輝)は、日本と海外をつなぐグローバル企業として、システム開発事業・人材派遣事業などを展開しています。
代表の三森は、かつて埼玉県警に勤務していた異色の経歴の持ち主。警察官時代、外国人の多い地域で治安維持にあたる中で、多くの葛藤や学びを得ました。
「対立ではなく対話を。排除ではなく共生を。」その原体験をもとに、国籍を越えた信頼のネットワークづくりをビジネスの軸に据えています。
LandBridge株式会社 代表取締役 三森 一輝
~Profile~

1995年、埼玉県生まれ。高校卒業後、埼玉県警に入庁。交番勤務や駅 前警備、外国人対応などに約7年間従事し、「対話の力」の重要性を実感する。
退職後はシステム開発会社に転職し、ゼロからプログラミングを学びエンジニアに転身。現場経験の中で、外国人労働者と日本社会の間にある“見えない壁”を痛感し、「ともに働き、ともに生きる社会」を目指して起業を決意。
2022年10月、ベトナム人の友人と共にLandBridge株式会社を設立。人と人、国と国をつなぐ“橋”となるべく、多国籍な人材が活躍できる社会づくりに挑んでいる。
【少年時代からの経営者への憧れとリーダー性】
印刷業を営む父を幼いころから尊敬し、「経営者は守るべきものがあるからこそ強い」と心に刻んできました。幼少期から野球に打ち込みましたが、弟・三森大貴さん(横浜DeNAベイスターズ所属)の才能の前に早々に道を譲ります。
それでも、自らの“人をまとめる力”に可能性を見出し、野球部のキャプテンや副部長を歴任。高校では体育科に進学し、毎日片道1時間の通学を自転車でこなすなど、地道な努力を重ねてきました。
【警察官、そして特殊部隊へ 「日本は外国人に優しくない」】
高校卒業後、「安定した仕事に就け」という父の助言を胸に、警察官としての道を歩み始めました。初任地は、外国人住民の多い川口市の交番。ここでの勤務は、人生観を大きく揺さぶる転機となります。訪れる人の約7割が中国やベトナムなどから来た外国人で、不法滞在者の摘発を行う日々の中、「なぜ彼らは逃げるのか」「なぜ共に働くことができないのか」といった疑問が芽生えていきました。
やがて、外国人一人ひとりの背景に目を向けるようになります。真面目に働くために「日本は良い国」と信じて来日したものの、過酷な労働環境に追い込まれ、逃げざるを得なくなる人々の存在を知ったのです。
「日本は好きだった。でも、実際に働いてみたら、想像とは違った」
夢を抱いて日本に来たにもかかわらず、劣悪な環境によってその夢を断たれる現実。その理不尽さに、正面から向き合うようになっていきました。
また、三森は、日々の職務質問や地域パトロールを通じて、外国人との言語や文化の壁を越えた“対話術”を磨いていきました。
駅前で10時間以上立ち続け、不審者を見逃さぬよう「人を見る目」を養いました。些細な挙動の変化を察知する鋭い観察力と、相手の警戒心を和らげる丁寧なコミュニケーション力が身についたのです。
一方で、特殊部隊(銃器対策部隊)へ抜てきされると、訓練は想像を絶するものでした。毎日500回以上の腕立て、30kgの防弾チョッキ、腰の感覚が消えるロープ降下訓練。
さらに「レンジャー訓練」では、30kg超の荷物を背負い山中を昼夜歩き続け、野ウサギをしめて食す極限のサバイバル体験も。「あれ以上の厳しさはない」と語るこの訓練が、三森に揺るがぬ自己信頼を与えました。
【コロナ禍で進路を転換「ITなら、いける」と確信】
特殊部隊員として活動する傍ら、埼玉県警の駅伝強化選手にも選ばれていた三森。
走ることが好きで、勤務後も毎日20キロを走り込むほど練習に打ち込んでいました。当時、弟がプロ野球ドラフトで指名されたこともあり、「兄として負けられない」という気持ちと、「駅伝大会で組織に貢献したい」という思いが彼の原動力となっていました。
しかし、転機は突然訪れます。コロナ禍により駅伝大会が中止され、異動先では希望とは異なる業務を任され、「組織の中では自分の選択が通らない」という無力感を抱くように。
悩み抜いた末、「好きなことをしなさい」という父の言葉に背中を押され、退職を決意します。
そこからは、社会の仕組みやビジネスについて一から学び直す日々。パソコンと本に没頭し、やがて「プログラミングなら自分にもできる」と手応えを感じ、猛勉強の末、未経験からIT企業への転職を果たしました。
新天地で与えられた任務は、ベトナム人エンジニアのオンラインマネジメント。これまで警察組織で培ってきたリーダーシップと統率力を活かし、1 年かけてシステム開発をやり遂げました。
国籍を超えたチームとの信頼関係の中で、「人種を越えて協働することの喜び」を初めて心から実感したのです。
【「自分より優秀な彼らが低賃金なのはおかしい」 日本とベトナムをつなぐ懸け橋を】
やがてフリーランスとして独立。そこで感じたのは、「日本のIT単価の異常な高さ」と「優秀な海外人材の不遇」。自らの価値観を揺さぶるこの“矛盾”に、三森は行動で答えます。
「だったら、自分が架け橋になろう」と即決。かつて共に働いたベトナム人たちへの感謝を胸に現地へ飛び、自らのネットワークを広げていきました。
こうして、2022年10月、27歳目前で設立されたLandBridge株式会社。
日本企業から受注したシステム開発を、ベトナムの優秀なエンジニアたちと共に納品するスタイルを確立。

オンライン体制を武器に次々と案件を成功に導き、1年目に年商3,500万円を達成後、2年目には倍の7,000万円、そして3年目(今期)はついに1億円超えを見込むまでに急成長。
わずか3年で3倍以上の売上規模へと躍進しています。

「人種も国籍も関係ない。大事なのは、お互いにリスペクトし、力を合わせること。日本の未来は、外国人とともに働ける社会をつくれるかにかかっていると思います」
―その言葉の奥には、警察官時代の苦悩、レンジャー訓練の極限、そして走り続けた青年の、誰にも負けない挑戦心があります。
29歳、三森一輝の物語は、まだ序章にすぎません。
-社長の一言-

治安を守る側として見ていた日本。今は、外国人と共に生きる社会を築く側に立ち、その中で強く感じるのは、“対話の力”の可能性です。
社名「LandBridge」には、“国境を越える架け橋になる”という想いを込めました。人種や国籍は関係なく、互いに敬意を持ち、力を合わせることこそが未来を拓く鍵だと信じています。
日本が少子高齢化という大きな課題を乗り越えるには、多様な背景を持つ人たちと共に働ける社会づくりが不可欠です。
国籍や立場の違いを超え、理解し合える社会を目指したい、あの川口の交番での経験こそが、今の私の原点です。
【AIと海外人材の融合で切り拓く、日本の未来型開発と採用のかたち】
LandBridgeでは、AIと海外人材を組み合わせた“次世代型の開発体制”を推進しています。
中でも注目されているのが、「バイブコーディング(Vibe Coding)」という新しい開発手法。
AIがコーディングの大部分を担い、人間のエンジニアが補助的に関わるスタイルで、開発の効率化と品質向上を実現します。
また、中小企業の悩みの一つである採用のミスマッチにもAIを活用。
AIが面接を行うサービス「NEXT HR AI面接官」では、採用担当者の負担を減らし、よりマッチした人材の採用を可能にします。
【会社概要】
会社名 : LandBridge株式会社
本社 : 〒343-0827 埼玉県越谷市川柳町2丁目401
代表取締役 : 三森一輝
事業内容 : DX支援、ソフトウェアの企画・開発・運用、UX/UIデザイン、プロダクトの企画・開発・運用
URL : https://landbridge.co.jp/
ビジネスeye
AIとオフショア開発を使ったシステム開発は、システム開発分野で急速に拡大し、進化しています。
市場動向と背景
- 日本を含む先進国ではIT人材不足が深刻化しており、特にAIエンジニアの需給ギャップは拡大しています。日本国内だけでも2025年にはAI人材が10万人以上不足すると予測されており、オフショア開発が不可欠な選択肢となっています。
- オフショア開発は、コスト削減と人材確保の両面で戦略的に活用されており、特にベトナムやアジア太平洋地域が主要な開発拠点として注目されています。
AI技術の進化とオフショア開発の変化
- 生成AI(例:GPTシリーズ、Google PaLM)やAutoMLなどの最新AI技術を活用した開発が主流となり、オフショア開発パートナーにもこれら技術への対応力が求められています。
- 生成AIの普及により、コード自動生成・テスト自動化・ドキュメント作成の効率化が進み、オフショア開発の役割や必要性が再定義されています。従来の「人月×コスト」モデルから、AI活用による生産性向上・品質向上へのシフトが進んでいます。
オフショア開発のメリットと課題
メリット
- コスト削減:国内開発と比べて最大50%近いコスト削減が可能な事例もあります。
- 人材確保:グローバルな優秀なAI人材にアクセスできる。
- 24時間開発:時差を活用した24時間体制の開発が実現しやすい。
- 生成AIによるスキルギャップの緩和やコミュニケーション補助が期待できる。
課題
- 要件定義や品質管理の難しさ:日本企業特有の曖昧な要件定義が、オフショア側と齟齬を生む原因となることが多い。
- コミュニケーション:言語・文化の壁や、AIツールの指示の明確化が必要67。
- 技術力の見極め:AIやクラウド、エッジAIなど最新技術への対応力がベンダー選定の重要な基準に。
具体的な活用事例
- 製造業での異常検知システム開発では、ベトナムのオフショアチームと協力し、AIによる画像認識や時系列分析を組み合わせたシステムを8ヶ月で開発。検出率向上・コスト45%削減・運用コスト30%削減などの成果が報告されています。
- 日本の大手SIerやメーカーでは、GitHub Copilotなどの生成AIツールを国内外の開発拠点で導入し、開発効率と品質の大幅な向上を実現しています。
今後の展望
- AIとオフショア開発の組み合わせは今後も拡大し、AI技術の進化とともに、より高度な技術領域(エッジAI、クラウドネイティブ開発など)への対応が求められる。
- 生成AIの進化により、オフショア開発の役割は「単なるコスト削減」から「グローバルなイノベーション推進」へと変化しつつあります。
まとめ
AIとオフショア開発を組み合わせたシステム開発は、コスト削減・人材確保・技術革新の観点から、2025年も日本企業にとって不可欠な戦略となっています。
生成AIの普及により開発効率と品質が向上する一方、要件定義やコミュニケーション、技術力の見極めなど新たな課題にも直面しています。
今後は、AI技術の進化に対応できるグローバルな開発体制の構築が、企業競争力の鍵となるでしょう。